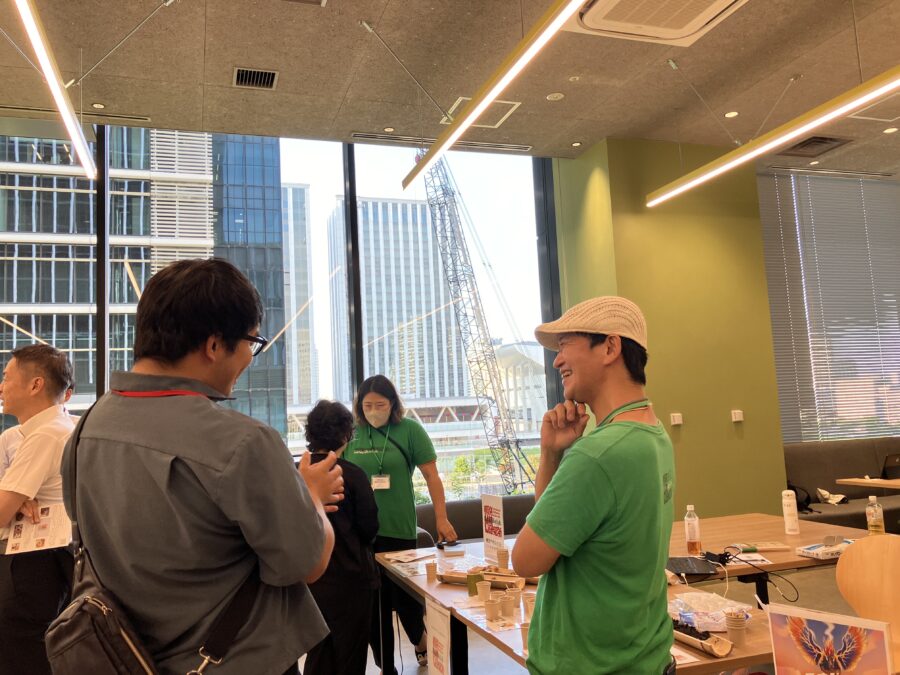横浜市環境保全協議会

横浜市環境保全協議会・横浜商工会議所 共催にて、8月28日(木)にサステナビリティセミナー「“捨てる”から“創る”へ 横浜からはじめる!アップサイクルで広がる可能性」を開催し、63名が参加しました。
横浜市における資源循環の取組から、市内を中心とした事業者による革新的なアップサイクル事例まで、環境担当者の皆さまはもちろん、すべてのビジネスパーソンにとって明日からのヒントが盛りだくさん。この記事では、セミナーのハイライトをダイジェストでお届けします!
【横浜発!】「捨てる」から「創る」へ!ワクワクが止まらないアップサイクル最前線セミナーレポート
横浜市資源循環局
官民連携でサーキュラーエコノミーを加速!
横浜市資源循環局からは、市が目指すサーキュラーエコノミー(循環型経済)の実現に向けた熱い想いが語られました。特に重視されているのは、製品の製造・供給側である動脈産業と、使用済み製品の回収・再生側である静脈産業の連携、すなわち「動静脈連携」です。この連携を加速するため、市は「横浜市資源循環推進プラットフォーム」を2024年10月に発足。企業間のマッチングや事業化支援を通じて、廃棄物の有効活用をサポートしています。

具体的な事例として、ホテルで廃棄予定だったフルーツをズーラシアの動物のおやつにするという、なんとも心温まる取組が紹介されました。これは、ザ・カハラ・ホテル&リゾート 横浜、藤ビルメンテナンス、ズーラシアが連携し、食品ロス削減と動物福祉を両立させる素晴らしいアイデアです。
さらに、食品廃棄物の抑制・再生利用・啓発に貢献する企業を表彰する「横浜市食の3Rきら星活動賞」や、食べ残し削減に取り組む飲食店を支援する「食べきり協力店事業」など、市民や企業を巻き込む多様な施策を展開。特に、お客様が料理をきれいに食べきると割引などの特典がもらえる「Clean Plate Yokohama」は、楽しく食品ロス削減に貢献できるユニークな企画です。市は、引き続き事業者との連携を強化し、気軽な相談窓口を通じて持続可能な社会の実現を目指しています。

株式会社Beer the First
食品ロスから生まれるクラフトビールの可能性!
アップサイクルの最前線を走る㈱Beer the Firstは、「廃棄になってしまうものを新しいものに変える」というコンセプトでクラフトビールを製造するスタートアップ企業です。彼らが着目したのは、パン、お菓子、寿司、弁当、麺類といった炭水化物の食品ロス。これらを麦芽の最大30%に置き換えることで、独自のクラフトビールを生み出しています。
同社の代表取締役社長 坂本 錦一 氏は、大手企業との連携に大きな可能性を見出しています。ESG投資が活発化する現代において、大手企業は環境配慮への取り組みを強く求められており、アップサイクル商品はその課題解決に貢献できるとのこと。今治市のオーガニックレモンを使ったレモンビール(J-AIR)や、さくらんぼの収穫支援と連携したクラフトラガー(JAL・JR東日本東北本部) を開発した事例は、その相性の良さを物語っています。自治体を巻き込んだ報告会では、メディア露出も期待できるなど、プロモーション効果も抜群です。

日本のエシカル市場はまだ発展途上ながら、大きな可能性を秘めていると坂本氏は語ります。クラフトビール市場におけるライト層からライトコア層へアプローチし、商品力とプロモーション力を兼ね備えた商品で市場を活性化させていきたいというビジョンは、新たなビジネスチャンスを予感させます。

神奈川県信用農業協同組合連合会(JA神奈川県信連)
地域農業と食の未来をつなぐアップサイクル戦略!
JA神奈川県信連からは、神奈川県の農業を支えるJAグループのアップサイクルへの取組が紹介されました。意外にも神奈川県で最も耕作面積が大きく、農家戸数が多いのが横浜市であり、JA横浜がその中心的な役割を担っています。
注目すべきは、横浜のブランド梨「浜なし」と「横浜メロン」の活用です。木の上で完熟させる「浜なし」は、生理障害(みつ症)などで味には問題ないが捨てざるを得ないもののうち有効利用できている涼は、年間約12トンにも及ぶそう。これをピューレや果汁化し、「いとしのやるJAん横浜カレー」「やるJAん浜なしサイダー」さらには浜なしを使ったグミ、といった商品に生まれ変わらせています。横浜メロンも、横浜美術大学の学生デザインを取り入れた「やるJAん横浜メロンサワー」として販売され、地域全体で盛り上げる「オール横浜」の取り組みとして注目を集めています。
また、食べられないトマトを、金融機関で小銭を置く「カルトン」に再生する「トマトカルトン」の事例は、JAならではのSDGs実践として非常にユニーク。ほかにもJA神奈川県信連は、過熟したいちごをスムージー事業を行う企業にマッチングするなど、ビジネスマッチングを通じて地域の食品ロス削減と農家支援を積極的に行い、「農業と地域の未来を創る」という理念を体現しています。

一般社団法人横浜竹林研究所
厄介者「竹」を地域資源に変える秘策!
一般社団法人横浜竹林研究所 代表理事の小林 隆志 氏からは、放置竹林が引き起こす深刻な問題(土砂災害リスク、住居への侵食、CO2排出、生態系への影響など)について警鐘が鳴らされました。横浜市内にも竹林が点在し、地域が抱える課題となっている現状。同研究所は「横浜の竹林を活用し、人と地域と笑顔をつなぐ」というビジョンのもと、この厄介者である竹林を資源に変える活動を展開しています。


その代表例が、竹林整備で伐採した幼竹(2~3mに育ったもの)を「ハマのメンマ」として製造販売するプロジェクト。これまで廃棄されていた幼竹が、美味しい食材にアップサイクルされることで、地域の竹林問題解決に貢献しています。さらに、「純国産メンマプロジェクト」として全国約150団体と連携し、国産竹の一貫生産にこだわった「クラフトメンマ」の普及にも力を入れています。キリンシティでの成功事例は、ストーリー性のある商品の強さを証明しています。
メンマだけでなく、竹をスイーツやイタリアン、フレンチなど様々な料理に活用する「竹菜」の開発も進行中。さらに、横浜市消防局で廃棄される消防ロープやホースを、鍋つかみやサコッシュ、子ども服などにデザインの力でアップサイクルするユニークな取り組みも。食を入口に竹林整備への関心を深め、竹の未利用資源活用に挑戦する彼らの活動は、まさに地域課題解決の鑑です。
その他のアップサイクル・地域貢献事業者からの挑戦!
イチゴス合同会社
横浜戸塚のバリアフリーいちご狩り農園「イチゴス横浜」。収穫時に出る規格外の完熟いちごを廃棄せず、冷凍保存して汎用性の高い「いちごソース」としてアップサイクル。ヨーグルトにかけるなど、その美味しさを地域に循環。食品ロス削減と、誰もが楽しめる農園づくりを両立させる、心温まる取り組みです。


株式会社エリアプロジェクト
横浜発の元気の源「エナジーハマー」は、横浜ビールの製造過程で廃棄されるモルト粕を再利用。ビールのコクと栄養を活かし、ビタミンの酸味をまろやかにする画期的なアイデア!地域企業や農家、B型就労支援施設も巻き込み、横浜全体で循環を生み出す、地域循環型エナジードリンクです。
株式会社kitafuku
㈱kitafukuは、「地域の課題を二人三脚で解決する」をビジョンに掲げ、クラフトビール醸造過程で大量に発生するモルト粕に新たな命を吹き込んでいます。通常は廃棄されるこのモルト粕を原料として再活用し、「クラフトビールペーパー」という再生紙を製造。単なる廃棄物ではなく、環境に配慮した魅力的な素材へと変身させ、循環型社会の実現に貢献しています。企業の環境担当者の方々にとって、こうしたユニークなアップサイクル素材は、新たなビジネス展開の可能性を広げるヒントとなるかもしれません。


合同会社グロバース
横浜の規格外野菜が美味しく生まれ変わる!グロバースは、乾燥技術で規格外野菜をアップサイクルした商品を企画・製造・販売。10月には泉区に、農家さんの商品開発支援や小学生の体験教室も開かれる食品加工所「たべるラボYokohama」を開業予定。食とアップサイクルを楽しく学べる、地域活性化の拠点となりそうです。
株式会社Gold Heart
神奈川初のクラフトコーラを手がけるGold Heart。傷のある規格外レモンや青みかんを美味しくアップサイクル。横浜長島農園の規格外椎茸を使った「神奈川ポテトチップス」や、コーラ製造後のスパイス残渣を和紅茶とブレンドしたシリーズも展開。CSVで地域課題解決と価値創造を両立しています。

横浜から広がるアップサイクルの未来に期待!
今回のセミナーでは、「捨てる」ものに「創る」喜びと価値を見出す、横浜のアップサイクルの多様な可能性が示されました。横浜市と事業者、そして市民が一体となって、限りある資源を未来へつなぐ。会場では、各ブースで新たなコラボレーションにつながる具体的なお話をする声が多く聞かれました。皆様の企業でも、ぜひこのアップサイクルの波に乗って、持続可能な社会の実現に向けて一緒に歩みを進めていきませんか?